
獣害対策支援システム
鳥獣害被害について
鳥獣被害の現状
近年、鳥獣被害は中山間地域を中心に全国的に深刻化・広域化しています。その背景として、森林伐採や都市化による生息地の減少、農地の拡大や新たな作物の導入が影響しています。また、シカやイノシシの個体数増加や気候変動も関与しています。加えて、防護策の不足や資金・技術の不備も被害の悪化を招いています。これらの要因が組み合わさり、鳥獣による被害が増加しています。
令和4年度のデータによると、野生鳥獣による農作物被害額は156億円に達しており、全体の約7割がシカ、イノシシ、サルによるものです。また、森林では年間約5000ヘクタールが被害を受けており、このうち約7割がシカによるものです。
水産業にも影響が及んでおり、河川や湖沼ではカワウによるアユなどの捕食、海面ではトドによる漁具の破損が深刻な問題となっています。これらの被害は、単なる経済的損失にとどまらず、営農意欲の減退や耕作放棄、離農の増加を招いています。また、森林では下層植生の消失による土壌流出や、希少植物の食害など、広範な影響が出ています。
これらの被害は、数字に表れる以上に農山漁村の生活や生態系に深刻な影響を及ぼしており、今後の対応策の強化が求められています。
鳥獣被害の対策
野生の動物が農作物や林業に被害をもたらす問題に対して、国と自治体が協力して、鳥獣被害の軽減に取り組んでいます。
国は令和3年の「鳥獣被害対策特別措置法」の改正により、強力な補助金制度を導入しました。この制度では、防護設備の設置に対する費用を補助し、電気柵やネットなどで農作物や森林をしっかり守れるようサポートしています。また、捕獲器の購入費用や駆除作業にかかる経費も補助対象となり、迅速な被害対応が可能になります。
さらに、被害実態の調査や対策研究にも支援があり、地域の実情に応じた効果的な対策の開発が進められています。地域協議会や対策組織にも支援が行われ、地域全体での協力体制の強化が図られています。
自治体では、地域の特性に応じた具体的な対策が実施されています。地元の農業協同組合や自治体の担当部署が、補助金制度の申請サポートや情報提供を行い、地域のニーズに即した支援を提供しています。また、地域住民と連携し、防護策や駆除活動の実施を促進しています。
シカ・イノシシ捕獲推移と目標
シシカやイノシシの捕獲頭数は、法改正前の数年間に比べて顕著に増加しています。2018年には年間の捕獲頭数が約40万頭だったのに対し、2023年には約60万頭に達しました。改正により、捕獲・駆除活動に対する支援が強化され、捕獲器の購入費用や駆除作業の経費が補助されるようになりました。この補助金制度が導入されたことで、地域や農家がより多くの資源を使ってシカやイノシシの捕獲に取り組むことが可能になりました。
例えば、シカやイノシシの捕獲頭数は、2018年には年間の捕獲頭数が約40万頭だったのに対し、2023年には約60万頭に達しました。
法改正により鳥獣被害対策を実施出来る自治体が増え、捕獲頭数は増加傾向にあります。
しかし生態系や農林水産業に深刻な被害を及ぼしている野生鳥獣について、国は更なる捕獲対策の強化を図り、個体数の減少を目指しています。
シカ・イノシシは生息頭数を平成23年度の生息頭数から令和10年度までに半減し、捕獲圧を維持することで、生態系や農林水産業への被害を軽減し、持続可能な管理を進めることを当面の目標と掲げています。
マップクエストの獣害対策
マップクエストでは鳥獣による農作物などの深刻な被害を解決する為、地元の公的機関や関係各所と連携して獣害対策システムを研究・開発しています。
出現予測情報を地図で見える化したり、目撃情報を位置とセットで収集するなどの取り組みがあります。目撃情報を取集し、出現予測を見える化することで、柵設置、捕獲、被害予防、さらには交通事故対策等に役立ちます。
これまでに以下の害獣に対応したシステムを開発しています。これら以外の獣害にも汎用的に対応するシステムをご用意する�ことも可能です。詳しくお知りになりたい方はお問い合わせください。
害獣及び対応システム
ニホンジカ

ニホンジカは、日本全国に広く分布し、古くから日本人に馴染む深い動物で「神の使い」として保護されてきた地域もあります。しかし近年様々な要因からニホンジカの生息域の増大と分布の拡大に伴い、農作物や森林の被害が全国的に拡大している傾向にあります。
ニホンジカは雑食性で、毒性のある植物以外はほぼすべての植物を食べることができます。そして食欲が旺盛で1日に何キロも食べるため、周囲に食べる植物が無くなったら、樹の皮を剥がして食べてしまい、そこから樹木の立ち枯れを起こしてしまうことがあります。
被害は農作物だけにとどまらず、人家の近くにやってくるシカが増えることで寄生虫による感染症の増加も懸念されます。また餌を求めて移動する鹿は、国道など大きな幹線道路を横切ることも多く、不意に飛び出してきたシカを避けられず事故を起こしてしまうケースも多く見られます。
これらの問題を解決すためにも、人とニホンジカの共生のため様々な取り組みが各地で実施されています。
シカの生態とその能力
繁殖力が強い
初産齢は2歳ですが、栄養状態が良ければ1歳でも妊娠。毎年春から夏にかけて1頭を出産します。寿命はオスが10~12年、メスが15~20年程度。
たいていの植物を食べる
特定の種類を除けば、ほとんどの植物を食べます。食物の減少する冬には落ち葉さえも食べて、生活をする ことができます。
群れで生活する
なわばりを持たず、群れを作って行動するため、食物の少ない時期の良いエサ場などでは、大集団になることがあります。
大食漢である
メスでも、1日に5kg以上の植物(生重)を食べる大食漢。毎年生えかわる角のため、春から夏のオスはさらに多くの食物が必要です。
移動能力が高い
数kmから数十kmを移動する能力があり、積雪地などでは、季節的移動で 積雪による影響を避けることができます。
跳躍能力が高い
身の危険を感じたときなどは、2m以 上もの大ジャンプ。
防護柵なども飛び 越えることがあります。
シカ害対策
シカの目撃情報の提供システムと 獣害対策支援アプリ
ニホンジカによる農作物の被害が深刻な問題となっている為、シカが出現する可能性の高い地域を把握し、罠設置場所の検討や駆除対象エリアの選定に役立て、効果的な対策を行うために、愛知県森林・林業技術センター(新城市)、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所、NPO法人 穂の国森林探偵事務所と連携し開発した、獣害対策支援システムです。
シカの出現予測情報を地図で見える化したり、目撃情報を位置とセットで収集するなどの取り組みがあります。
獣害による問題
毎年、大量駆除しているにも関わらず、シカの繁殖スピードに追いついていません。主な原因は、シカの駆除には猟師の勘や経験に頼る傾向があり、出現する可能性が高い場所の把握や共有が難しかったため、効果的な対策が出来ていない点にあります。
システム効果
地図を利用することにより、これまでのGPSを使って収集したデータを簡単にマッピングができます。
シカの出現する可能性の高いエリアを一目で把握することができるようになったため、効果的な罠の設置場所や駆除エリアの選定が容易になりました。また、地域住民がスマートフォンやタブレットのアプリで、シカの目撃情報、足跡情報や食害情報を登録することができます。
担当職員が寄せられた情報を定期的に地図に反映し、情報の精度を高めていくことにより、より効果的な対策を期待できます。
獣害対策支援アプリ「やるシカない」
獣害対策支援アプリ「やるシカない!」は、シカによる獣害対策のための無料アプリケーションです。
このアプリは、主に野生動物による農作物被害や交通事故を防ぐために、農家や自治体、一般の人々が利用することができます。
アプリを利用することで、野生動物の出没情報や被害状況をリアルタイムで共有することができます。また、被害にあった場合には、その被害の種類や場所を記録することができ、その情報を元にシカ柵設置、捕獲、被害予防、さらには交通事故対策等の獣害対策に役立てられます。
シカ密度の現状把握
お住まいの地域にどれだけのシカがいるかを把握できます。
シカ出現予測
シカが出現しやすい地区を把握できます。その地区内の獣道にワナをしかけることで効率よく捕獲できます。
シカ目撃地点
シカ被害地点
シカ情報マップに寄せられた情報を示しています。


シカの目撃情報の提供システム「シカ情報マップ」


「シカ情報マップ」は、シカの目撃情報を提供するシステムです。このシステムは、一般の人々がシカの目撃情報を投稿することにより、シカの出没地域を共有し、被害を防ぐことを目的としています。
ユーザーがシステムに目撃情報を投稿すると、その情報がマップ上に表示され、他のユーザーが閲覧することができます。この情報は、シカが出没する可能性の高い地域や時間帯を把握するために役立ちます。
ス�マートフォンのアプリケーションとして提供されており、誰でも無料で利用することができ、シカ害を防ぐための地域の協力体制を構築するために、有用なツールとなっています。
スマホやPCで
どこからでも報告
シカの目撃情報や被害情報をスマートフォンやインターネットに接続したパソコン等から報告できます。
リアルタイムで地図上に更新
報告された情報は、リアルタイムで地図上に更新され、過去の情報と合わせてすぐに確認できます。
全国の目撃・
被害情報を閲覧
愛知県だけの情報ではなく、全国で目撃情報や被害情報を報告、閲覧することができます。
「シカ情報マップ」と「やるシカない!」の相互活用
「シカ情報マップ」で提供されるシカの目撃情報を「やるシカない!」が活用し、利用者にとっての最適な対策方法を提供することができます。たとえば、「シカ情報マップ」でシカの発生地域や行動パターンを確認し、それに基づいて「やるシカない!」で対策方法を提案することができます。
逆に、「やるシカない!」で報告された獣害被害情報を「シカ情報マップ」にフィードバックすることで、より正確なシカの分布情報を収集することができます。これにより、「シカ情報マップ」の情報がより精度の高いものとなり、より効果的な獣害対策が可能となります。
つまり、「シカ情報マップ」と「やるシカない!」は、それぞれが持つ情報を相互に活用することで、より効率的かつ正確な獣害対策が実現できます。
愛知県森林林業技術センターでは、これまでもシカの情報を収集する取り組みを行ってきましたが、情報の提供者は行政機関や森林組合等、森林・林業の関係者が中心でした。
この「シカ情報マップ」ができたことにより、地域の住民や一般の方等から広く情報を収集できるようになりました。
また、愛知県だけの情報ではなく、全国で目撃情報や被害情報を報告、閲覧することができます。

.jpeg)
-
シカの目撃ポイント、被害ポイントを地図上にプロット。
-
250m四方毎のシカの存在確率で、地図を色塗り。
-
目撃情報と存在確率からフェンスや罠の設置などの獣害対策を立てられる。
-
※ シカの目撃ポイント、被害ポイントは2015年1月~2017年10月の間に愛知県森林・林業技術センターに寄せられた情報を収録しています。
※ 収録しているエリアは愛知県の中山間地のみとなります。
シカの目撃情報をお寄せください
シカや植栽木の食害を見かけた際は、スマホやパソコンから「シカ情報マップ」のWebページにアクセスして情報提供をお願い致します。
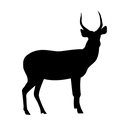

シカ情報マップ:https://shikadoko.animalenq.jp/
カミキリムシ
クビアカツヤカミキリは、サクラやモモ、ウメ、スモモなどのバラ科樹木に寄生し、幼虫が樹の内部を食べて枯らしてしまう外来のカミキリムシです。
日本では2012年に愛知県で最初の被害が確認されましたが、その後、埼玉県、徳島県、群馬県など12都府県(2022年2月現在)に侵入してサクラ並木や果樹園などに大きな被害をもたらしており、2018年1月に「特定外来生物」に指定されました。
クビアカツヤカミキリは、春から夏にかけて地上で成虫として活動し、木の表面を傷つけたり、葉っぱを食べたりすることもあります。その後、成虫は地中に潜り、卵を産みます。孵化した幼虫は、地中で木の根元や幹部分を食害して成長します。被害を受けた木は徐々に枯れていき、最終的には枯死してしまうこともあります。
クビアカツヤカミキリによる被害は、特に人工林や広葉樹林で深刻な問題となっています。被害に遭った木を伐採しても、周囲にいる成虫が次々と新たな木に寄生し、被害が広がっていくため、防除が困難とされています。
このため、林業や農林業関係者は、クビアカツヤカミキリによる被害を防ぐため、予防的な対策を取ることが求められています。

カミキリムシ対策
早く見つけてしっかり伐る
クビアカツヤカミキリアンケート
クビアカツヤカミキリの分布拡大が続いており、その拡がりは市町村の境や県境を越えて生じています。
被害先端地域での被害の早期発見には、周辺地域での被害状況に基づく侵入警戒が重要です。そのためには、行政区を超えた情報共有が重要となります。
近隣での被害発生を知り侵入を警戒するために、クビアカツヤカミキリの被害アンケートサイトを作りました。
被害を見つけた時にその場でスマートフォンからアンケートを送信できます。
また、被害を見つけた場所を記録しておいて�、後にパソコンのウェブブラウザーからもアンケートを提出できます。










